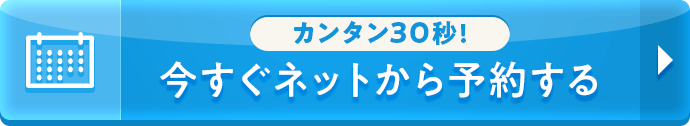埼玉県における歯科口腔保健の現状
投稿日:2025年08月3日
最終更新日:2025年07月31日

埼玉県における歯科口腔保健の現状:県民の意識・行動と公衆衛生的課題に関する分析
Part 1: 埼玉県民における口腔健康への意識の浸透:高い関心と行動の乖離
本章では、埼玉県民の歯科口腔保健に対する意識の現状を分析する。各種調査から明らかになるのは、県民が自身の歯と口の健康に対して極めて高い関心を持っているという事実である。しかし、その高い関心は必ずしも予防的な行動に結びついておらず、「意識と行動のパラドックス」とも言うべき状況が存在する。このパラドックスの構造を理解することは、今後の埼玉県の歯科保健施策を効果的に推進する上で不可欠な第一歩となる。
1.1 高水準で維持される健康への関心
埼玉県が実施した県政サポーターアンケートによれば、自身の歯と口の健康に「関心がある」と回答した県民の割合は89.2%に達しており、9割弱が強い関心を示していることがわかる 。この数値は、過去の同様の調査(令和5年実施)における87.1%という結果からも微増しており、県民の口腔健康に対する意識が安定して高い水準にあることを示している 。この高い関心は、単なる一時的なものではなく、県民の間に広く定着した価値観であると評価できる。
この関心の背景にある動機を深く掘り下げると、県民が口腔健康をより広範な生活の質(QOL)の文脈で捉えていることが明らかになる。歯と口の健康に関心を持つ最も大きな理由として挙げられたのは、「いつまでも健康でいたい」であり、回答者の半数以上(52.8%)を占めた 。これは、歯の健康が単に口内の問題に留まらず、全身の健康、すなわち「健康寿命」を支える基盤であるという認識が浸透していることを示唆している。次いで多かった理由は「美味しく食事がしたい」(40.5%)であり、口腔機能が日々の喜びや生活の豊かさに直結する重要な要素として認識されていることがうかがえる 。
これらの動機は、伝統的な歯科医療のイメージである「痛みからの解放」や「虫歯の治療」といった対症療法的な、あるいはネガティブな動機付けとは一線を画す。むしろ、県民は「健康を維持し、人生を長く楽しむ」という、極めてポジティブで未来志向の視点から自らの口腔健康を見つめている。この事実は、今後の公衆衛生活動や啓発キャンペーンを展開する上で、非常に重要な示唆を与える。恐怖や不安を煽るのではなく、県民が既に持っている「より良く生きたい」という前向きな欲求に訴えかけるアプローチが、より高い効果を発揮する可能性を示している。
1.2 全身の健康との関連性に関する知識の浸透
埼玉県民の高い関心は、口腔健康が全身の健康に及ぼす影響についての具体的な知識によって裏付けられている。県民は、口腔ケアが単に口の中を清潔に保つ行為以上の意味を持つことを理解している。調査では、「20本以上自分の歯を保つことは、健康寿命の延伸につながる」という知識を持つ人が75.3%、「よく噛むことは認知症の予防につながる」と認識している人が72.1%にものぼった 。
これらの数値は、厚生労働省や日本歯科医師会が長年にわたり推進してきた「8020運動(80歳になっても20本以上自分の歯を保とう)」のような国民的な健康キャンペーンが、埼玉県内においても深く浸透し、その理念が県民の知識として定着していることの証左である 。埼玉県自身も、新たな「埼玉県歯科口腔保健推進計画」の策定にあたり、糖尿病などの生活習慣病と歯周病の関連性や、口腔機能の低下(オーラルフレイル)が全身の機能低下(フレイル)につながるという科学的知見を計画の根拠として重視している 。県民の知識レベルと県の政策方向性が一致している点は、今後の施策推進における強力な追い風となるだろう。
このように、埼玉県民は口腔健康の重要性を「知っており」、その理由も「理解している」。この知識基盤は、より高度な予防行動へと県民を導くための貴重な資産である。問題は、この豊富な知識と高い関心が、なぜ日々の具体的な行動、特に専門家による定期的なケアの受診に必ずしも結びつかないのかという点にある。
1.3 「意識と行動のパラドックス」の提起
本報告書で繰り返し論じる中心的なテーマは、この「意識と行動のパラドックス」である。すなわち、県民の89.2%が口腔健康に高い関心を持ち、その重要性に関する知識も豊富であるにもかかわらず、後述するように、定期的な歯科検診の受診や、問題発生前の予防的介入といった具体的な行動には大きな壁が存在する 。
このパラドックスは、公衆衛生上の極めて重要な課題を浮き彫りにする。それは、知識の提供や意識の啓発だけでは、人々の行動を変えるには不十分であるという事実である。人々が「重要だ」と知っていることと、「今、自分が行うべきだ」と感じることの間には、深い溝が存在する。
この溝を埋めるためには、行動を阻害している具体的な要因を特定し、それらを一つひとつ取り除いていく戦略的なアプローチが求められる。それは、単なる情報提供の強化ではなく、受診のハードルを下げるためのロジスティクス改善、行動経済学的な視点を取り入れた動機付け、そして何よりも「症状がない時こそ専門的ケアが必要である」という、予防医療の核心的な価値観を社会に根付かせるための、粘り強いコミュニケーション戦略が必要となる。
以降の章では、この「意識と行動のパラドックス」が、県民の日常生活、専門家との関わり、そして世代間の違いの中で、具体的にどのように現れているのかを詳細に分析していく。
Part 2: 日常の口腔ケア実践と専門的ケアの利用実態:パラドックスの解体
本章では、前章で提起した「意識と行動のパラドックス」を、埼玉県民の具体的な行動データを通じて解体していく。日々の歯磨き習慣から、かかりつけ歯科医の有無、そして定期検診の受診率とその障壁に至るまで、県民の行動パターンを詳細に分析することで、高い意識がなぜ行動に結びつかないのか、そのメカニズムを明らかにする。
2.1 自宅での口腔ケア習慣:盤石だが不完全な基盤
埼玉県民の自宅でのセルフケア習慣は、一定のレベルに達している。1日に歯を磨く頻度について尋ねた調査では、「1日2回」が45.6%、「1日3回以上」が30.1%であり、合計で75.7%の県民が1日に2回以上の歯磨きを実践している 。これは、口腔衛生の基本的な習慣が広く国民に浸透していることを示すものであり、公衆衛生活動の成果として高く評価できる。この強固な基盤は、さらなる予防行動を構築する上での出発点となる。
しかし、この歯磨き習慣だけでは不十分である可能性も指摘しなければならない。歯ブラシによる清掃だけでは、歯と歯の間(歯間部)や歯と歯肉の境目(歯周ポケット)のプラーク(歯垢)を完全に取り除くことは困難であり、虫歯や歯周病の多くはこれらの部位から発生する。県の調査でも、歯ブラシに加えた補助的な清掃用具(歯間ブラシやデンタルフロスなど)の使用状況が問われており、これが口腔ケアの質を左右する重要な要素であることが示唆されている 。歯磨きの回数が多いことが、必ずしも質の高いケアを意味するわけではなく、むしろ「毎日しっかり磨いている」という自己評価が、専門家によるチェックの必要性を感じさせにくくする「偽りの安心感」につながっている可能性は否定できない。
また、オーラルフレイル(口腔機能の軽微な低下)に関する自己評価チェックの結果も、この点を裏付けている。「1日2回以上、歯を磨く」と回答した割合は62.0%であったのに対し、「1年に1回以上、歯科医院を受診している」と回答した割合は55.0%に留まった 。これは、セルフケアを実践している人々の中にも、専門的なケアを受けていない層が一定数存在することを示しており、セルフケアへの過信がプロフェッショナルケアから遠ざける一因となっている可能性を示唆している。
2.2 「かかりつけ歯科医」の存在:両刃の剣
埼玉県民の歯科医療システムへのアクセスにおいて、特筆すべき点は「かかりつけ歯科医」の保有率の高さである。実に77.6%の県民が、「日頃から治療や相談ができるかかりつけの歯科医師(歯科医院)がいる」と回答している 。これは非常に高い数値であり、県民と歯科医療機関との間に信頼関係が構築されていることを示す、埼玉県の医療インフラにおける大きな強みである。全国的な調査でも、信頼できるかかりつけ歯科医の存在が、歯科受診に対する不安を和らげる最も重要な要因であることが示されている 。
しかし、この「かかりつけ歯科医」の存在は、諸刃の剣となる側面も持っている。その役割が、県民によってどのように認識されているかが問題となる。理想的には、かかりつけ歯科医は、病気の治療だけでなく、定期的な検診や予防指導を通じて、患者の生涯にわたる口腔健康を維持・増進する「健康パートナー」であるべきだ。
しかし、データは別の側面を映し出す。かかりつけ歯科医を持つ人が77.6%いる一方で、過去1年間に歯科検診を受けた人は64.1%に留まる 。単純計算で、かかりつけ歯科医がいるにもかかわらず、少なくとも13.5%の人々は定期的な予防ケアのためにその歯科医院を訪れていないことになる。これは、多くの県民にとって、かかりつけ歯科医が「何か問題が起きた時に頼る、信頼できる治療者」として位置づけられており、「問題が起きるのを防ぐために定期的に通う、予防のパートナー」とは必ずしも認識されていないことを示唆している。この認識のギャップこそが、予防歯科医療の普及を阻む根深い課題の一つである。
2.3 歯科サービス利用のパターン:予防的介入 vs 対症療法的治療
埼玉県民の歯科サービスの利用パターンは、大きく3つのグループに分類できる。
- 予防的行動グループ: このグループは、口腔健康への高い意識を具体的な行動に移している層である。県の調査で、過去1年間に歯科検診(健診)を「受けた」と回答した64.1%がこれに該当する 。この数値は、厚生労働省が実施した令和4年の全国調査における受診率58.0%を上回っており、埼玉県がこの重要な予防指標において全国平均を凌駕していることを示している 。これは、県の歯科保健施策や、個々の歯科医院によるリコールシステムの努力が結実した、特筆すべき成果である。
- 対症療法的行動グループ: このグループは、歯科医療を「問題解決の手段」と捉えている層である。歯に痛みを感じたり、口の中に違和感があった際の行動として、「すぐに歯科医院へ行く」と回答した53.4%がこの中心をなす 。一見すると、迅速な対応は望ましい行動に思える。しかし、これは裏を返せば、自覚症状が出現するまで歯科医院を訪れないという「対症療法的(リアクティブ)」な姿勢の表れでもある。痛みや違和感は、多くの場合、病状がある程度進行したサインであり、この段階での受診は、より複雑でコストのかかる治療につながりやすい。
- 受診回避グループ: 少数派ではあるが、症状があっても「しばらく様子を見る」あるいは「市販薬で対処する」といった行動をとるグループも存在する 。この層は、歯科医療に対する障壁が特に高いと考えられ、より深刻な口腔疾患に発展するリスクを抱えている。
この3つのグループの存在は、県民の行動が一様ではないことを示している。公衆衛生上の目標は、対症療法的行動グループと受診回避グループを、いかにして予防的行動グループへと移行させていくかという点に集約される。
2.4 予防的ケアを阻む障壁の解体
では、なぜ約35.9%の県民は、口腔健康への関心が高いにもかかわらず、過去1年間に歯科検診を受けなかったのか。その理由は、意識と行動の間の溝の正体を解き明かす鍵となる 。
調査で示された検診を受けない理由の上位3つは、ほぼ同率で並んでおり、極めて示唆に富んでいる。
- 「必要性を感じない」(35.2%): これが最も根深く、本質的な障壁である。自覚症状がない限り、自分の口は健康であると判断し、専門家によるチェックの必要性を認識できない。これは、Part 1で述べた高い健康意識と真っ向から矛盾する、認知的不協和の典型例である。虫歯や歯周病といった主要な歯科疾患が、初期段階ではほとんど自覚症状なく進行する「サイレント・ディジーズ(静かなる病気)」であることが、一般に十分に理解されていない。
- 「時間がない」(34.2%): これは物理的な制約に見えるが、その本質は優先順位の問題である。人々は、真に必要かつ重要だと認識している事柄のためには、時間を捻出する。つまり、「時間がない」という理由は、しばしば「歯科検診は他の用事よりも優先順位が低い」という価値判断の現れである。
- 「予約が手間である」(34.1%): これは、受診プロセスにおける具体的な摩擦(フリクション)である。電話予約の煩わしさ、希望の日時が取れないといった経験が、受診への意欲を削いでいる。
注目すべきは、この調査において「費用」が上位の障壁として挙げられていない点である。これは、少なくともこの回答者層においては、問題が経済的なものではなく、主に心理的・認知的な障壁と、利便性というロジスティクス上の障壁にあることを示している。
この分析から導き出される結論は明確である。予防歯科医療の普及を阻む最大の敵は、「無関心」ではなく、「根拠のない安心感」と「行動の先延ばしを正当化する低い優先順位」である。したがって、今後の施策は、この心理的な壁を打ち破ることに主眼を置く必要がある。
以下の表は、県民の心の中に存在するこの認知的不協和を視覚的に示したものである。高い理想(関心の理由)と、日常的な現実(行動しない理由)が並存している状況が、一目瞭然となる。
| 関心の動機(なぜ気にかけるのか) | 回答率 (%) | 行動の障壁(なぜ検診を受けないのか) | 回答率 (%) |
|---|---|---|---|
| いつまでも健康でいたい | 52.8 | 必要性を感じない | 35.2 |
| 美味しく食事がしたい | 40.5 | 時間がない | 34.2 |
| (その他) | – | 予約が手間である | 34.1 |
この表が示すのは、政策立案者や医療提供者が向き合うべき課題の核心である。問題は県民の意識の低さにあるのではない。むしろ、その高い意識を、具体的な「予防行動」という出口へと導くための、効果的な道筋を提示できていないという点にある。その道筋とは、第一に、自覚症状のない口腔内に潜むリスクを可視化し、「必要性」を創出する教育。第二に、予約システムの簡便化や診療時間の柔軟化など、行動の「手間」を徹底的に削減する環境整備である。この両輪を同時に回すことこそが、パラドックスを解消する鍵となる。
Part 3: 世代間の意識格差と口腔健康における新たな潮流
口腔健康に対する価値観や悩み、そして行動は、ライフステージを通じて一様ではない。特に、若年層と中高年層では、その関心の対象が大きく異なり、それぞれに特有の課題が存在する。本章では、全国的な調査データを援用しつつ、埼玉県内でも同様に存在すると考えられる世代間の意識格差を分析する。さらに、現代の食生活の変化がもたらした、若年層における咀嚼機能の低下という、見過ごされがちな新たな公衆衛生的課題に警鐘を鳴らす。
3.1 若年層の審美性への強い希求(10代~20代)
10代から20代の若年層にとって、口腔健康は「機能」や「疾患予防」といった側面よりも、「見た目(審美性)」という側面が極めて強い関心事となっている。全国規模の意識調査によれば、この世代の歯や口に関する悩みのトップは「歯の色」と「歯並び」であり、他者からの視線を強く意識した悩みが大半を占める 。
この審美性への高い関心は、具体的な行動へと結びついている。2024年に実施された調査では、10代・20代の44%が「歯列矯正を検討している」または「すでにしている」と回答しており、30代(34.7%)や40代(26.2%)と比較して突出して高い数値を示している 。この傾向は、就職活動や結婚といったライフイベントを控えた未婚層で特に顕著であり、美しい口元が社会的・個人的な成功における重要な資産と見なされていることを示唆している 。
さらに、このトレンドは新型コロナウイルス感染症のパンデミックを経て、より一層加速した。長期間のマスク生活が終わり、これまで隠されていた口元が再び注目されるようになったことで、多くの人々、特に女性の間で歯の見た目に対する意識が急激に高まった。ある調査では、マスク緩和後に約60%が「歯の見た目」への関心を強め、約70%が「ホワイトニング」への関心が高まったと回答している 。20代・30代女性が今後取り組みたい美容トレンドとして、「ホワイトニング」と「歯列矯正」が上位を占めており、審美歯科市場の大きな牽引力となっている 。
この若年層の審美性への強い動機は、公衆衛生の観点から見れば、極めて有効に活用しうる「入り口」である。なぜなら、美しい歯並びや白い歯を実現し、それを維持するためには、良好な口腔衛生状態と健康な歯周組織が不可欠だからである。矯正治療中のプラークコントロールの重要性や、ホワイトニング効果を長持ちさせるための定期的なクリーニングの必要性など、審美的な目標を達成するプロセスの中に、包括的な口腔健康管理の重要性を自然な形で組み込むことができる。彼らの「美しくなりたい」という強い欲求を、生涯にわたる健康習慣を確立するための絶好の機会と捉え、戦略的にアプローチすることが可能である。
3.2 中高年層における機能性への関心のシフト(40代以上)
ライフステージが進むにつれて、口腔健康に対する関心の焦点は「審美性」から「機能性」へと明確に移行する。40代以上になると、最も大きな悩みとして浮上してくるのが「歯と歯の間にものが挟まる」という、具体的な機能障害である 。これは、加齢に伴う歯肉の退縮や、歯周病の進行によって歯間に隙間が生じること、あるいは歯がわずかに移動することによって起こる典型的な症状である。
この悩みは、単なる不快感に留まらない。それは、より深刻な問題である歯周病の存在を示唆する重要なサインである。全国調査によれば、歯周病の指標である4mm以上の歯周ポケットを持つ人の割合は、年齢とともに顕著に増加する 。また、定期的な歯科検診の受診率も、年齢が高い層ほど高くなる傾向がある 。これは、中高年層が自らの身体の変化を通じて、口腔機能の低下を「自分自身の問題」として実感し、専門家の助けを求めるようになるからに他ならない。彼らにとっては、抽象的な「健康のため」というスローガンよりも、「食べ物がうまく噛めない」「ものが挟まって不快だ」といった日々の具体的な経験こそが、受診への最も強力な動機となる。
この世代交代に伴う関心のシフトをまとめたのが以下の表である。若年層と中高年層が、口腔健康に関して全く異なる世界観を持っていることが明確に見て取れる。
| 指標・関心事 | 若年層(18~29歳) | 中高年層(40歳以上) |
|---|---|---|
| 主な歯の悩み | 1. 歯の色 2. 歯並び |
1. 歯と歯の間にものが挟まる |
| 歯列矯正への関心 | 高い(44%が検討・経験済み) | 低下傾向(40代: 26.2%, 50代: 17.5%) |
| 定期検診受診率 | 全体平均より低い傾向 | 全体平均より高い傾向 |
| 主な動機 | 審美性、見た目の改善 | 機能性の維持・回復、不快感の解消 |
この分析は、画一的なメッセージングがいかに非効率であるかを物語っている。若年層には「理想の笑顔を手に入れるための第一歩」として予防ケアを位置づけ、中高年層には「これからの人生も美味しく食事を楽しむためのメンテナンス」としてその価値を訴求するなど、ターゲットの心に響く言葉で語りかける、セグメント化されたコミュニケーション戦略が不可欠である。
3.3 現代社会が生んだ新たな危機:若年層における咀嚼機能の低下
これまでの歯科保健が主に「虫歯」と「歯周病」という二大疾患との戦いであったのに対し、今、水面下で新たな危機が進行している。それは、若年層における「噛む力(咀嚼機能)」の発達不全という問題である。
全国調査が明らかにした実態は衝撃的である。10代の若者のうち、48.3%が「食事で噛んでいると顎が疲れることがある」と回答しており、この割合は70代の2.7倍にも達する 。さらに、10代の40.3%が「硬い食べ物を噛み切れないことがある」と訴え、全体の半数以上が「硬い食べ物より柔らかい食べ物が好き」と回答している 。好きな食感のランキングでも、30代以上が「さくさく」を好むのに対し、10代・20代では「もちもち」が1位となるなど、食の嗜好そのものが軟食化している傾向が顕著である 。
これは、現代の食生活がもたらした、見過ごすことのできない「静かなる流行(サイレント・エピデミック)」である。加工食品の普及により、子供の頃からあまり硬いものを噛む習慣がなかった世代において、顎骨や咀嚼筋が十分に発達しないまま成長している可能性が強く示唆される。この問題は、埼玉県においても例外ではないと考えられる。
咀嚼機能の発達不全は、長期的に見て深刻な健康問題へと連鎖する危険性をはらんでいる。十分に噛むことができないため、消化器系への負担が増加する。硬い野菜や繊維質の多い食品を避けるようになり、栄養バランスの偏りを招く。そして何より、オーラルフレイル(口腔機能の虚弱)の早期発症につながり、将来的な全身のフレイルや、認知機能の低下リスクを高める可能性がある。
埼玉県では、子供の虫歯が着実に減少しているという喜ばしい成果が見られる一方で 、この「噛む力」の問題は、次世代の口腔健康における新たな、そしてより根深い課題として浮上している。疾患の予防だけでなく、「健全な口腔機能の育成」という視点を、今後の歯科保健計画の重要な柱として位置づけることが急務である。これは、学校教育における食育の強化、家庭への情報提供、そして歯科医療専門家による早期の機能評価と指導といった、多角的なアプローチを必要とする、次なる挑戦である。
Part 4: 埼玉県の口腔健康ランドスケープに関する公衆衛生的評価
本章では、これまで分析してきた県民の意識と行動のデータを、より広範な公衆衛生の文脈の中に位置づける。埼玉県の口腔健康に関する各種指標を全国平均と比較し、県の政策目標と照らし合わせることで、その達成度と課題を客観的に評価する。さらに、県の歯科医療提供体制についても分析し、地域全体の口腔健康を支えるインフラの現状を明らかにする。
4.1 全国水準との比較による埼玉県のパフォーマンス評価
埼玉県の口腔健康レベルを客観的に評価するため、主要な全国指標との比較を行う。
8020運動の達成状況: 「80歳で20本以上の歯を有する」ことを目指す8020運動は、国民の口腔健康のバロメーターである。厚生労働省の令和4年歯科疾患実態調査によると、全国の8020達成者(75歳以上85歳未満の数値から推計)の割合は51.6%であった 。これは、国民の2人に1人が目標を達成していることを意味し、日本の歯科保健の大きな成果である。埼玉県の最新の達成率に関する直接的なデータは本調査資料には含まれていないが、県の第3次歯科口腔保健推進計画(2019-2023年度)においても、この達成は重要な目標として掲げられており、県がこの指標を重視していることは明らかである 。また、県民の間で8020運動の理念が広く認知されていること(75.3%が「20本以上の歯を保つことが健康寿命につながる」と認識)は、目標達成に向けた良好な土壌があることを示している 。
歯周病の罹患状況: 歯周病は、成人の歯を失う最大の原因であり、国民的な健康課題である。全国調査では、成人の47.9%が4mm以上の歯周ポケット(中等度以上の歯周病の指標)を有している 。これは極めて高い罹患率であり、多くの国民が自覚症状のないまま歯周病に罹患している実態を示している。埼玉県に特化した近年の成人歯周病有病率の精密なデータは限られているが、過去のデータや調査からは高い罹患率が示唆されており 、県の健康計画においても歯周病対策は主要な課題として認識されている 。前章で述べたように、40代以上の県民の最大の悩みが「歯にものが挟まる」であるという全国的な傾向 は、埼玉県においても歯周病が広く蔓延していることを強く示唆している。
歯科検診受診率: 予防行動の最も重要な指標である定期検診の受診率において、埼玉県は特筆すべき成果を上げている。県の調査による過去1年間の歯科検診受診率は64.1%であった 。これは、令和4年の全国平均58.0% 、および令和5年の国民健康・栄養調査における58.8% を明確に上回る数値である。この事実は、埼玉県が県民の予防行動を促進する上で、全国的に見ても先進的な取り組みを行っており、それが一定の成果を上げていることを示している。この高い受診率は、県の公衆衛生上の大きな成功事例であり、その成功要因を分析し、さらなる向上を目指すことが重要である。
4.2 主要な成功事例と根強い課題
埼玉県の口腔保健施策は、顕著な成功と、依然として残る根強い課題の両側面を持っている。
成功事例:小児う蝕(虫歯)の著しい減少: 埼玉県における最大の成功事例は、子供の虫歯が大幅に減少していることである。県の報告によれば、3歳児および12歳児のう蝕はともに減少傾向にあり、特に3歳児の一人平均う蝕歯数は、平成30年度の一時的な増加を除き、その後は順調に減少している 。令和4年の県平均う蝕歯数は0.4本と、10年前の半分にまで減少した 。この背景には、埼玉県歯科医師会と連携したフッ化物洗口事業の推進や、学校歯科保健活動の充実など、長年にわたる地道な予防活動の積み重ねがある 。これは、ターゲットを明確にし、科学的根拠に基づいた介入を継続的に行うことで、公衆衛生上の大きな成果を上げられることを示す好例である。
根強い課題:成人期以降の歯周病対策: 小児期の成功とは対照的に、成人期以降の歯周病は依然として最大の課題である。歯周病は自覚症状に乏しく、静かに進行するため、Part 2で分析した「必要性を感じない」という受診障壁と直結している。県民の多くが、歯周病のリスクを自分自身の差し迫った問題として認識できていない。この「見えざる敵」に対して、いかにして県民の注意を喚起し、予防行動へとつなげていくかが、今後の8020達成率向上や健康寿命延伸の鍵を握っている。
根強い課題:要配慮者への歯科医療提供体制: もう一つの重要な課題は、障害者や在宅の要介護高齢者など、自力での歯科医院への通院が困難な人々への対応である。これらの人々は、口腔内の問題を抱えやすく、それが全身の健康状態の悪化やQOLの低下に直結しやすい。埼玉県では、この課題を認識し、第3次推進計画において、在宅歯科医療を実施する登録医療機関数を2018年の783機関から2023年度までに1,200機関へ増やすという具体的な数値目標を掲げ、体制の拡充に努めている 。この取り組みの継続と強化が、県が目指す「健康格差の縮小」を実現する上で不可欠である。
4.3 歯科医療提供体制の現状
埼玉県の口腔健康は、県内に広がる歯科医療機関のネットワークによって支えられている。さいたま市などの都市部を中心に、一般歯科から矯正歯科、審美歯科、インプラントといった高度な専門治療を提供する多数の歯科医院が存在し、県民の多様なニーズに応える体制が整っている 。
この医療提供体制を支える専門職人材に目を向けると、歯科衛生士の平均年収は埼玉県で約381万円であり、全国平均(約376万円)をわずかに上回る水準にある 。これは、県内の労働市場がある程度の魅力を維持していることを示唆する。しかし、隣接する東京都の平均年収(約410万円)と比較すると見劣りする部分もあり、人材の確保と定着は継続的な課題である 。
より深刻な問題は、医療資源の地域的な偏在である。歯科衛生士の求人数を見ると、さいたま市、川越市、越谷市といった主要都市に著しく集中している 。これは、歯科医師や最新の医療設備についても同様の傾向があると推測される。この地理的な偏在は、県の推進計画が掲げる「健康格差の縮小」という理念に対する直接的な挑戦である。都市部に住む住民は、質の高い予防ケアや専門治療に容易にアクセスできる一方で、交通の便が悪い地域や過疎地域の住民は、限られた選択肢しか持てない可能性がある。このアクセス格差が、結果として口腔健康状態の格差へとつながることは想像に難くない。
一方で、埼玉県歯科医師会およびその地区支部は、公的な医療提供体制を補完する重要な役割を担っている。歯と口の健康フェスティバル、学校での保健指導、各種コンクールといった啓発活動を通じて、地域住民の健康意識の向上に貢献している 。また、県の計画に沿った在宅歯科医療の推進や、障害者歯科相談など、行政と密接に連携した活動も展開しており、県の歯科保健施策における不可欠なパートナーとなっている 。
Part 5: 埼玉県の口腔健康を前進させるための戦略的提言
本報告書の分析を通じて、埼玉県民の口腔健康に関する意識の高さと、それが必ずしも行動に結びつかない「パラドックス」の存在、世代間の価値観の違い、そして新たな公衆衛生的課題が明らかになった。本章では、これらの分析結果を統合し、埼玉県の口腔健康をさらに前進させるための、具体的かつ実行可能な戦略的提言を行う。これらの提言は、県が策定を進める新たな「埼玉県歯科口腔保健推進計画」(第4次)の方向性と軌を一にするものである。
5.1 分析結果の総括
本報告書で明らかになった主要な点を以下に要約する。
- 中心的な課題:「意識と行動のパラドックス」
埼玉県民は自らの口腔健康に極めて高い関心(89.2%)を持っているが、その意識が定期的な予防行動に結びついていない。このギャップの核心には、「自覚症状がないため、検診の必要性を感じない」という根深い認知の壁が存在する。 - 主要な挑戦
- 成人の歯周病対策: 小児う蝕の抑制には成功しているが、成人の歯を失う最大の原因である歯周病は、依然として「静かなる脅威」として広く蔓延している。
- 若年層の咀嚼機能低下: 軟食化社会を背景とした、若者の「噛む力」の低下という新たな危機が進行しており、将来的な健康リスクをはらんでいる。
- 世代間の価値観の相違: 若年層は「審美性」、中高年層は「機能性」を重視しており、画一的なアプローチでは効果的な介入が困難である。
- 医療資源の地理的偏在: 歯科医療資源が都市部に集中しており、県が目指す「健康格差の縮小」を阻む要因となる可能性がある。
- 活用すべき資産
- 高い「かかりつけ歯科医」保有率: 県民の77.6%が信頼できる歯科医を持っており、これは予防活動の強力なプラットフォームとなりうる。
- 全国を上回る歯科検診受診率: 64.1%という高い受診率は、県のこれまでの取り組みの成果であり、さらなる向上への基盤となる。
- 活発な歯科医師会の活動: 県および地区の歯科医師会は、地域に根差した啓発活動や公的事業において、行政の重要なパートナーである。
5.2 「埼玉県歯科口腔保健推進計画」との整合性
本報告書の分析結果と提言は、県の第3次計画(2019-2023年度)および今後策定される第4次計画の基本理念と完全に整合するものである。県の計画が掲げる「生涯にわたる歯科疾患の予防」「健康格差の縮小」「定期的な歯科検診の促進」といった目標 に対し、本報告書は、その目標達成を阻んでいる具体的な障壁(例:「必要性を感じない」という認知)を特定し、それを乗り越えるためのエビデンスに基づいた戦略を提供するものである。例えば、「定期歯科検診の促進」という目標を達成するためには、単に「検診を受けましょう」と呼びかけるだけでなく、なぜ人々が検診を受けないのか、その根本原因である「必要性の認識不足」に直接働きかける必要があることを示している。
5.3 ターゲットを明確にした政策および公衆衛生的介入
上記の分析に基づき、以下の5つの戦略的提言を行う。
-
提言1:「必要性の再定義」キャンペーンの展開
ターゲット: 口腔健康に関心は高いが、定期検診は受けていない「意識先行・行動停滞層」(検診未受診者のうち「必要性を感じない」と回答した35.2%の層)。
アクション: 歯科受診の概念を、「痛みや問題が生じた際に行く場所」から「自覚症状のない病気を早期に発見するための必須の健康スクリーニング」へと転換させるための、戦略的な公衆衛生マーケティングキャンペーンを実施する。その際、県民に馴染みのある健康診断とのアナロジー(類推)を用いることが有効である。「心臓発作が起きてからではなく、血圧を測るために健康診断を受けるように、歯が痛くなってからではなく、静かに進行する歯周病を見つけるために歯科検診を受けるのです」といった、具体的で分かりやすいメッセージを通じて、予防の価値を訴求する。これは、で特定された最大の認知障壁に直接対処するものである。
-
提言2:若年層の「審美性への動機」を健康増進に活用
ターゲット: 10代から20代の若年層。
アクション: 埼玉県歯科医師会と連携し、矯正歯科や審美歯科を提供する医療機関向けに、カウンセリング時に健康に関するメッセージを自然に組み込むためのガイドラインや患者向け資材を開発・提供する。例えば、「理想的な笑顔の土台は、健康な歯ぐきと骨です。矯正治療を成功させるために、まずはプロによるクリーニングで最適な口内環境を整えましょう」といった形で、審美的な目標達成と健康維持が不可分であることを強調する。これにより、で示された若年層の強い動機を、包括的な口腔健康習慣の確立へとつなげることができる。
-
提言3:「噛むんと埼玉」育成イニシアチブの創設
ターゲット: 幼児、学童、思春期の子供たち。
アクション: 従来の「う蝕予防」中心の学校歯科保健プログラムに、「咀嚼機能の健全な育成」という新たな柱を導入する。具体的には、多様な食感の食品をバランス良く摂取することの重要性や、顎の発達を促すための簡単なエクササイズなどを、児童生徒や保護者向けの教育モジュールとして開発・展開する。給食の献立に噛みごたえのある食材を意識的に取り入れるよう、栄養士や学校関係者との連携を強化する。これは、で示された咀嚼機能低下という新たな危機に対する、先を見越した予防的介入である。
-
提言4:「かかりつけ歯科医」ネットワークの予防活動への動員
ターゲット: かかりつけ歯科医を持つ県民77.6%。
アクション: 埼玉県歯科医師会 と協力し、所属する患者集団において、高い定期検診リコール率や歯周病の維持管理率を達成した歯科診療所を認定・表彰する制度を創設する。これにより、個々の歯科医院のインセンティブを、治療中心から予防中心へとシフトさせる。かかりつけ歯科医を、単に「問題が起きた時に頼れる存在」から、地域住民の健康を積極的に守り育てる「公衆衛生の能動的な担い手」へと変革させることを目指す。
-
提言5:地理的格差の可視化と是正
ターゲット: 県および市町村の保健医療計画担当者。
アクション: 県内の人口分布に対し、歯科医療サービス(特に歯科衛生士による予防ケアや専門治療)の提供体制がどのように分布しているかを詳細にマッピングする調査を実施する。その結果を用いて、医療資源が手薄な地域を特定し、移動歯科診療車の巡回、遠隔での口腔保健指導(テレヘルス)の導入、過疎地域で勤務する歯科専門職へのインセンティブ付与など、地域の実情に応じたターゲット介入策を立案・実行する。これは、県の推進計画が最重要目標の一つとして掲げる「健康格差の縮小」 を具現化するための、データに基づいたアプローチである。
これらの提言は、埼玉県民が既に持つ高い健康意識を、具体的な行動と生涯にわたる健康へと結実させるためのロードマップである。意識と行動の間の溝を埋め、すべての県民が質の高い口腔保健の恩恵を受けられる社会を実現するために、県、市町村、歯科医師会、そして県民一人ひとりが連携し、これらの戦略を実行に移すことが強く望まれる。