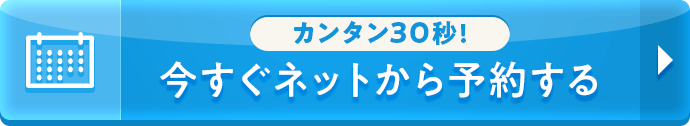歯を大切に!シリーズ12「歯の黄ばみ・黒ずみ」について
投稿日:2024年10月14日

セルフホワイトニングに興味がある皆さんと一緒に歯について学ぶシリーズ、第12回目のテーマは「歯の黄ばみ・黒ずみ」です。
幼い頃は真っ白だったのに、大人になると何故、歯の色が黄ばんだり黒ずんだりしてしまうのでしょうか?
今回は、「歯の黄ばみ・黒ずみ」について調べてみます。
目次
人種ごとの歯の特徴
黄色人種に比べ、白人や黒人は歯が白い印象がありませんか?
歯並びを美しく整え、定期的なホワイトニングで白い歯を維持するなど、歯に関する意識が高い文化であることが理由のひとつに挙げられると思います。
しかし、人種ごとの根本的な歯の質の違いも理由のひとつなのです。
エナメル質は真っ白ではなく、半透明の組織であり、すぐ下に存在している象牙質を少しだけ透過しています。
黄色人種は象牙質が黄色い上、その外側のエナメル質が薄いため、歯の色が黄ばんで見えてしまうのだとか。
上の前歯の裏側はくぼんでいることが多く、これをシャベル状切歯といいます。
歯の形が丸くて大きいので歯並びが悪くなりやすく、お手入れもしづらいことが特徴です。
逆に、白人や黒人は、歯の表面のエナメル質が厚く、エナメル質の下の象牙質の色が白に近いため、歯が白く見えやすいのだそう。
前歯は細長くすっきりした形です。
それぞれの歯も平面的で小さいため、隙間なく綺麗に並びやすいことが特徴です。
後天的な理由も
人種的な理由以外に、後天的な黒ずみや黄ばみの原因もあります。
◉酸蝕(さんしょく)
酢・柑橘類・清涼飲料水・炭酸飲料など、酸性の強い飲食物のせいで歯が溶ける現象です。
健康に良いとされる食品には酸性のものが多く、長年摂り続けていると少しずつ歯の表面が溶かされ、象牙質が露出して歯が黄色く見えるようになります。
◉咬耗(こうもう)
自分の歯と歯が擦れ合って磨り減り、歯の象牙質が表面に現れ、色が濃く見えます。
加齢現象でも起こりますが、歯ぎしりや食いしばりがひどい人も注意が必要です。
◉神経を抜いた
虫歯が進行して歯の神経を抜くと、年数が経つにつれ、歯の色が黒ずんできます。
神経の周囲の象牙質にはコラーゲンが含まれていますが、神経の処置後には血液循環がなくなるため、年数が経つにつれ変質します。
◉神経が死んだ
周囲の歯に比べて1本だけ色が黒い場合、歯の神経が死んでいる可能性があります。
歯を強くぶつけた衝撃や内出血が原因で内部の血液循環がおこなわれず、周囲の象牙質のコラーゲンが変質し、歯が黒く変色していきます。
◉加齢
年齢を重ねると表層のエナメル質が薄くなり、象牙質の厚みが増すため、黄色みを強く感じるようになります。
さらには、歯の表面への刺激により細かなヒビが生じ色素が入り込むことも、歯の色を濃くさせる原因だと考えられます。
◉うがい薬の影響
グルコン酸クロルヘキシジン系の洗口剤を使っている場合、長く使用していると、歯の表面に茶色っぽい着色が起こることがあります。
◉詰め物の変色
自身の歯の黄ばみではなく、過去の治療で使用されたプラスチックの詰め物が変色している場合もあります。
プラスチックは傷つきやすく吸水性があるため、月日が経つにつれて黄ばんできます。
最後に
ステインやタバコのヤニの蓄積が原因の場合は、表面を綺麗にすることで印象がかわることも。
当店には、歯の表面の汚れを落とすクリーニングもありますから、ぜひお試しくださいね。
美しい口元は健康から!
口腔環境を整えて、歯の白さをより楽しんでいただきたいと思います。
歯科医師 岡本恵衣

経歴
2012年 松本歯科大学歯学部卒業
2013年 医療法人スワン会スワン歯科にて臨床研修
2014年 医療法人恵翔会なかやま歯科
2020年 WhiteningBAR(株式会社ピベルダ)