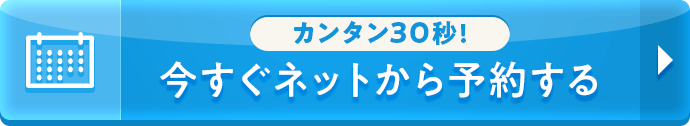ホワイトニングに関するFAQまとめ
投稿日:2025年10月11日

専門家レポート:歯のホワイトニング徹底解説 Q&A(決定版)
I. ホワイトニングの基礎知識:定義、作用機序、効果の限界
A. 歯が黄ばむ原因と、医療ホワイトニングのメカニズム
歯の黄ばみは、主に二つの要因によって引き起こされます。一つは、歯の構造的な問題であり、最も外側の透明度の高いエナメル質の内側にある、黄味を帯びた象牙質の色が透けて見えるためです。もう一つは、日常の飲食物や喫煙などによって生じる、歯の表面へのステイン(着色汚れ)の蓄積です。
歯科医院で行われる医療ホワイトニングは、この黄ばみの根本原因、すなわち象牙質の色自体を変化させることを目的としています。施術には、主に過酸化水素や過酸化尿素といった強力な薬剤が使用されます。これらの薬剤は、歯の内部(象牙質)まで浸透し、黄ばみの原因となっている色素分子に対し、化学的な酸化還元反応を誘発します [1]。この反応により、色素分子は細かく分解され、無色化されるため、歯全体が内部から明るく、白く漂白されるのです。
この漂白治療は、歯を溶かしたり削ったりすることなく実施されるため、安全性が確立されています [1]。ホワイトニングは25年以上前にアメリカで始まった治療法であり、国家資格を持つ歯科医師や歯科衛生士の厳密な管理のもと、口腔内に入れても安全な薬剤が使用されています [1]。
B. 医療ホワイトニング(漂白)とセルフホワイトニング(清掃)の決定的な違い
ホワイトニングを検討する上で最も重要な理解は、歯科医院で行われる医療ホワイトニングと、サロンなどで提供されるセルフホワイトニングとの作用機序の決定的な相違点です。
歯科医院でのホワイトニングは、薬機法に基づき「歯の内部から白くする」作用を持つ医薬品(過酸化物系薬剤)を使用できる、専門的な医療行為です [1]。これにより、もともとの歯の色以上に白くする「漂白」効果が期待できます。
一方、セルフホワイトニングでは、法的な規制により医薬品(漂白剤)を使用することができません。このため、セルフホワイトニングの作用機序は、あくまで歯の表面の汚れを物理的または化学的に「清掃」する程度の効果にとどまります [1]。セルフホワイトニングで謳われる「歯が白くなる」という効果は、内部の色を変える漂白ではなく、表面のステインを除去することで本来の歯の色に近づけることを意味します。作用機序が根本的に異なるため、セルフホワイトニングに何回通ったとしても、歯の内部の色素を分解し、陶器のような真っ白な色(ブリーチシェード)を達成することは不可能です [1]。
この規制の存在は、医療ホワイトニングの費用が相対的に高くなる根本的な理由にも関連しています。歯のエナメル質を漂白する高純度の薬剤は、歯科医師の厳密な診療と処方を受けなければ使用できず、コストが高くなる傾向にあるためです [2]。すなわち、効果の天井は使用できる化学物質の制限によって法的に定められているため、真のホワイトニング効果を求めるのであれば、医療機関での施術が必要となります。
C. 施術後の効果レベル:限界値への到達方法
ホワイトニング効果の現れ方には個人差がありますが、一般的に、1回のオフィスホワイトニング施術で平均2〜4段階のシェードアップ(白さの向上)が短時間で実感できます [1]。
しかし、黄ばみが濃い歯を、陶器のような真っ白な色(ブリーチシェード)まで一度に到達させることは、どのホワイトニング方法を用いても不可能です [1]。理想的な、もともとの色を凌駕する「限界値の白」を目指す場合、段階的な治療計画が不可欠となります。
黄ばみの濃い歯を最短で限界値に近づけるためには、歯科医院でのオフィスホワイトニングを複数回実施するか、オフィスホワイトニングと自宅でのホームホワイトニングを組み合わせた「デュアルホワイトニング」を併用することが推奨されます [1]。具体的な回数や期間については、患者の歯質、元の色調(シェード)、日々の食生活などによって大きく異なるため、専門的なカウンセリングを通して正確な計画を立てることが求められます [1]。
II. 種類別比較:オフィス、ホーム、デュアル、セルフの徹底解析
ホワイトニング方法は、即効性、持続性、費用、手間の四つの観点から、それぞれの目標やライフスタイルに応じて選択することが重要です。
A. オフィスホワイトニング(Office Whitening: OW)
オフィスホワイトニングは、歯科医師または歯科衛生士が歯科医院内で施術を行います。高濃度の過酸化水素/過酸化尿素を主成分とする薬剤を歯に塗布し、熱や光を照射することで化学反応を促進します。この方法の最大の特長は、即効性が非常に高いことです。短時間で歯が白くなるのを実感でき、特定のイベントを控えている方や、短期間での効果を強く求める方に適しています [3]。費用相場は、1回あたり約20,000円から50,000円程度です [2]。高濃度の薬剤を使用するため、歯1本あたりの薬剤費も1,000円から4,000円程度と高くなる傾向があります [2]。
B. ホームホワイトニング(Home Whitening: HW)
ホームホワイトニングは、歯科医院でカスタムメイドされたマウスピースと、低濃度の薬剤(例:過酸化尿素10%など)を用いて、患者自身が自宅で継続的に行う方法です。即効性はオフィスホワイトニングに劣りますが、時間をかけて薬剤を浸透させるため、白さが深く定着し、長期間にわたって持続しやすいという大きなメリットがあります [3]。費用相場は、マウスピース製作費と薬剤費を含め、約20,000円から40,000円程度です [2]。
C. デュアルホワイトニング(Dual Whitening: DW):最高の効果と持続性の追求
デュアルホワイトニングは、オフィスホワイトニングの即効性と、ホームホワイトニングの持続性を組み合わせた、最も強力で効果的なホワイトニング方法です [2, 3]。
この方法では、まずオフィスホワイトニングで一気に歯の色を明るくし、その後、ホームホワイトニングで白さを定着・強化させます。その結果、他のどの方法よりも高いホワイトニング効果が期待でき、施術後すぐに白さを実感できるだけでなく、その効果を1年以上と最も長く維持できる点が特徴です [3]。色戻りを最小限に抑えたい方や、歯の色を限界値まで追求したい方に最適な選択肢とされています [2]。
デメリットとしては、費用が最も高額になる点です。一般的な費用相場は、約50,000円から80,000円程度、またはそれ以上になることもあります [2, 3]。また、通院と自宅での毎日のマウスピース装着(時間的な手間)の両方が必要となります [3]。しかし、長期間の審美性を確保し、頻繁な再施術コストを避けるという観点から、最終的には最も費用対効果が高いと評価される場合も少なくありません。
D. セルフホワイトニング(Self Whitening: SW)
セルフホワイトニングは、医療機関以外で行われる、表面の清掃を主目的とした方法です。自宅用キットやサロンでの施術が含まれ、医薬品を使用できないため、歯の内部を漂白することはできません [1]。費用相場は、自宅用キットで約1,500円から30,000円程度、サロンでの施術で約6,000円から20,000円程度と、他の方法に比べて安価です [2]。
以下に、主要なホワイトニング方法の特徴を比較した表を示します。
ホワイトニング種類別 詳細比較表
| 種類 | 施術場所 | 主な薬剤濃度 | 即効性 | 持続期間(目安) | 費用相場(概算) | 最大のメリット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オフィス | 歯科医院 | 高濃度 (例: 30%) | 高い (即時実感) | 3ヶ月〜6ヶ月 | 20,000〜50,000円 | 短期間で高い白さを実現 |
| ホーム | 自宅 | 低濃度 (例: 10%) | 低い (数日後から) | 6ヶ月〜1年 | 20,000〜40,000円 | 白さの後戻りが少なく、歯を傷めにくい |
| デュアル | 併用 | 併用 | 非常に高い | 1年以上 | 50,000〜80,000円 | 最高レベルの白さと持続性 [2, 3] |
| セルフ | サロン/自宅 | 医療外成分 | 低い (表面清掃) | 短期間 | 1,500〜20,000円 | 手軽さ、コストの低さ(漂白効果なし) |
III. 副作用とリスク管理:知覚過敏の発生機序と対処法
知覚過敏(歯がしみる症状)は、ホワイトニング施術において最も頻繁に報告される一時的な副作用です [4]。知覚過敏は、歯の表面にあるエナメル質が薄くなったり、内部の象牙質が露出したりしている状態で、刺激が象牙質の内部の神経に伝わることで発生します [4]。
A. なぜ歯がしみるのか?知覚過敏を引き起こす臨床的要因の詳細
知覚過敏の発生には、ホワイトニング薬剤の作用だけでなく、患者の既存の口腔内状態が大きく関与しています。薬剤が刺激となる主な原因は以下の5つです。
- 虫歯(カリエス): 虫歯によってエナメル質が溶かされている箇所があると、ホワイトニングジェルが容易に象牙質に到達し、強い痛みが発生しやすくなります [4]。このため、ホワイトニングを安全に行うには、事前の虫歯治療が必須となります。
- 歯周病による歯肉退縮: 歯周病が進行し、歯茎が下がると、通常は歯茎に覆われている歯の根元が露出します。歯の根元には元々エナメル質が存在しないため、露出した象牙質に薬剤が触れることで知覚過敏が起こりやすくなります [4]。
- 歯の摩耗や損傷: 歯ぎしりや食いしばりといった強い物理的な力により、エナメル質の表面が削れて薄くなっているケースがあります。表面が削れていると、薬剤が象牙質に与える刺激が増し、しみやすくなります [4]。
- 歯にクラック(小さなヒビ)がある: 固い食べ物を食べたときの衝撃などが原因で歯に小さなヒビ(クラック)が入っていると、その亀裂を通じて薬剤の刺激が深部に強く伝達され、痛みが強く出ることがあります [4]。
- ホワイトニングジェルの濃度が強い: 薬剤の漂白力が強力であるほど、歯がしみるリスクは高くなります。オフィスホワイトニングの薬剤濃度は概ね30%と高濃度であるのに対し、ホームホワイトニング(10%程度)は比較的低濃度であるため、ホームホワイトニングの方が知覚過敏の可能性は低くなります [4]。
これらの構造的な欠陥(虫歯、歯周病、クラック、摩耗)がある場合、薬剤は特定の部位に過剰に浸透しやすくなります。この現象こそが、知覚過敏の多くの症例が施術そのものよりも、患者の既存の口腔内健康状態に起因していることを示しています。したがって、安全かつ効果的なホワイトニングを実施するためには、包括的な歯科治療計画の一環として、事前にこれらの基礎疾患を全て治療することが臨床的に極めて重要となります。
B. 歯がしみたときの具体的な5つの対処法
知覚過敏はあくまで一過性の症状であり、通常はホワイトニング後24時間以内には自然におさまることが大半です [4]。しかし、痛みが強い場合の具体的な対処法は以下の通りです。
- 知覚過敏抑制成分を含む歯磨き粉の使用: 知覚過敏用の歯磨きジェルには、刺激を抑える作用のある硝酸カリウムが含まれています。これは象牙細管を通じての神経伝達を抑制する効果が期待できます [4]。また、フッ素にはエナメル質を強化し、象牙質を保護する働きがあるため、フッ素配合の製品も有効です [4]。
- 鎮痛剤の服用: 痛みが激しい場合には、市販の鎮痛剤(例:「ロキソニンS」など)を服用することで痛みを一時的に和らげることができます [4]。ただし、痛みが持続する場合は、知覚過敏以外の、未治療の虫歯などが原因である可能性もあるため、必ずクリニックで相談する必要があります [4]。
- 知覚過敏抑制剤の使用: 歯科クリニックで処方される知覚過敏抑制剤を、ホワイトニングジェルと同じようにマウスピースに注入し、15〜60分程度装着することで、痛みを和らげることができます [4]。一部のホワイトニングキットには、抑制剤が同梱されている場合もあります。
- 刺激物の回避: ホワイトニング直後は、歯が非常に敏感な状態にあるため、症状の悪化を防ぐためにも、冷水でのうがい、極端に熱い飲み物、レモンや香辛料など冷たいもの、熱いもの、刺激のあるものを口に含む行為を避けるべきです [4]。
- ホームホワイトニングの場合:装着時間の調整: ホームホワイトニング中に知覚過敏が強く出た場合は、通常2時間と定められているマウスピースの装着時間を一時的に短く調整することで、薬剤刺激を軽減できます [4]。
IV. 施術後の食事・生活習慣の徹底解説:色戻り防止マニュアル
ホワイトニング直後の歯は、再着色のリスクが非常に高まるデリケートな状態にあります。この時期に適切な飲食物の選択とケアを行うことが、効果を最大限に引き出し、維持するために不可欠です [5]。
A. 食事制限が必要な科学的理由
ホワイトニング後に色の濃い飲食物や酸性の強いものを避けるべき科学的理由は、歯の生理的変化に関連しています [6]。
- ペリクル(保護膜)の剥離: 薬剤の作用により、歯の表面を覆っていたタンパク質の保護膜である「ペリクル」が一時的に剥がれてしまいます [5, 6]。ペリクルが剥がれたエナメル質は最も無防備な状態であり、飲食物に含まれる色素を非常に吸着しやすくなっています。
- 歯の乾燥(脱水状態): 施術直後は歯が一時的に脱水状態にあるため、外部からの色素を吸収しやすい状態になっています [6]。
B. 制限期間の目安と行動指針
色の濃い飲食物や酸性度の高い飲食物を避けるべき期間は、ホワイトニングの種類と使用する薬剤の濃度によって目安が異なります [6]。
| ホワイトニングの種類 | 食事制限期間(目安) |
|---|---|
| オフィスホワイトニング | 施術後から24時間〜48時間 [6] |
| ホームホワイトニング | 施術後から1〜2時間 [6] |
特にオフィスホワイトニングは高濃度の薬剤を使用するため、歯がデリケートな状態が長く続きやすく、最低でも24時間、可能であれば48時間の注意深い食事管理が求められます。
C. 避けるべき飲食物の完全リスト:着色性、酸性度、イソフラボン
制限期間中は、以下の三つのカテゴリーに該当する飲食物を徹底的に回避することが、色戻りを防ぐ鍵となります。
1. 色素沈着を引き起こすもの(着色性の高い飲食物)
色の濃い飲料や食品は、剥離したペリクルの代わりに歯の表面に吸着し、早期の再着色を招きます [7]。
- 飲料の例: コーヒー、紅茶、日本茶、コーラ、赤ワイン。
- 食品・調味料の例: カレーライス、醤油、味噌、色の濃い漬物、キムチ、デミグラスソース、トマトソース、チョコレート、色の濃いフルーツ(ブドウ、ベリー系)。
- 注意点: タバコのヤニも強力な着色源であり、この期間は喫煙も控えるべきです。
2. 歯に刺激を与えやすいもの(酸性度の高い飲食物)
ペリクルが剥がれた状態の歯は、酸に非常に敏感です。酸性度の高いものは知覚過敏の症状を悪化させるだけでなく、エナメル質の再石灰化を妨げる可能性があります [5, 7]。
- 例: レモン、酢、マスタード、わさび、からし、香辛料を多く含む料理。
- 飲料の注意点: 炭酸飲料やスポーツドリンクは、たとえ無色透明であっても酸性度が高いものが多いため、避けるべきです [7]。
3. 化学的な着色原因となるもの(ポリフェノール・イソフラボン)
色が薄い飲食物の中にも注意が必要なものがあります [5]。
- 例: 豆腐、豆乳、納豆などの大豆製品。
- 理由: 大豆製品に含まれるイソフラボンは、着色しやすいポリフェノールの一種であり、歯の黄ばみにつながる可能性があるため、制限期間中は避けることが推奨されます [5]。
D. 制限期間中におすすめの飲食物
制限期間中は、色が白く、色素が薄く、中性で刺激の少ない食品を選択することが推奨されます [7]。
- 主食・タンパク質: 白米(おかゆ)、食パン、白身魚、しらす、鶏肉(塩味の焼き鳥など)、うなぎの白焼き、オムレツ。
- 乳製品・菓子: 牛乳、チーズ、ヨーグルト(無糖・プレーン)、パンナコッタ、シュークリーム(カスタードや生クリーム)、ナッツ類、ホワイトチョコレート。
- 飲み物: 水、ノンアルコールビール、お吸い物。
E. 着色を防ぐための食後の行動指針とリカバリー
飲食物が歯の表面に触れている時間を短縮することが、着色防止の最も重要な戦略です。
- 水分摂取の徹底: 食事前や食事中にこまめに水を飲むことで、口腔内の乾燥を防ぎ、唾液の分泌を促進し、着色成分を洗い流す効果が期待できます [6]。
- 速やかな歯磨き: 食事後は、可能な限りすぐに歯磨きを行い、歯の表面についた色素を物理的に取り除くことが推奨されます [6]。外出時などで歯磨きが難しい場合は、うがいで代替することが重要です。
- リカバリー対応: 誤って色の濃い飲食物を摂取してしまった場合は、「歯を白くする」成分(ステイン除去成分)が配合された歯磨き粉を用いてすぐに歯を磨き、色素が定着する時間を最小限に抑えるよう努める必要があります [5]。
V. 効果を長期間維持するためのメンテナンス戦略
ホワイトニングの効果は時間の経過とともに徐々に薄れる「色戻り」が避けられません。長期間、白さを維持するためには、この色戻りの原因となる再着色を予防し、歯質を修復する日常的なメンテナンス戦略が不可欠です [8]。
A. 色戻りのメカニズムと定期的なメンテナンス
色戻りの主な原因は、ホワイトニング直後に剥がれたペリクルが再形成される過程で、飲食物や生活習慣(喫煙など)の色素が取り込まれることです。また、一時的に多孔質化・脆弱化した歯の表面にステインが再付着することも原因となります。
白さを高水準で維持するためには、日常的なケアに加えて、数ヶ月に一度など、定期的に「軽くホワイトニング」(タッチアップ)を行うことが最も効果的であるとされています [8]。
B. ホワイトニング効果を維持する専門的な歯磨き粉の選び方
ホワイトニング後の歯は研磨力の高い歯磨き粉を使用すると再着色や知覚過敏を引き起こすリスクがあるため [9]、使用する歯磨き粉は「再着色を防ぐ」成分と「歯質を修復・強化する」成分の両方を含むものが推奨されます。
歯の白さを維持し、歯質を強化するために推奨される成分は以下の通りです。
| 成分名 | 主な働き | 臨床的役割 |
|---|---|---|
| ポリリン酸ナトリウム / ピロリン酸ナトリウム | ステインの分解、再付着の防止(再着色抑制) | 歯の白さの長期維持をサポート [9, 10] |
| ハイドロキシアパタイト(ナノ粒子) | エナメル質の修復・再石灰化促進 | 歯のくすみやザラつきを改善し、象牙質を保護 [9, 10] |
| 硝酸カリウム | 象牙細管の神経伝達抑制 | 知覚過敏症状の予防と緩和 [4] |
| フッ素(例: 950ppm) | エナメル質の強化・象牙質保護 | 歯質を強化し、再石灰化を促す [4, 9] |
| ポリエチレングリコール (PEG) 400 | タバコのヤニを溶かす清掃効果 | 喫煙などによる特定の強い着色汚れに対応 [11] |
これらの成分の選択は、単なる「白くする」作用に留まらず、漂白によって一時的にデリケートになった歯の表面構造を修復し、色素の定着しにくい滑らかな状態を化学的に作り出す「二重の化学的アプローチ」を実現するために重要です。特にハイドロキシアパタイトやフッ素による歯質修復過程を省略すると、歯の多孔質化が続き、効果が著しく短縮する可能性が高まります。
VI. 安全性・禁忌事項に関する詳細レビュー
ホワイトニングは一般的に安全な施術ですが、特定の生理的状態や既存の疾患を持つ患者に対しては、施術が強く制限されるか、完全に禁忌とされています。
A. ホワイトニングができない対象者リスト(禁忌事項)
以下の対象者は、安全性を考慮し、施術を避けるべきとされています [12]。
- 小児(〜高校生)
- 妊娠中の方、授乳中の方
- 無カタラーゼ症の方
- 光線過敏症の方
B. 妊娠中・授乳中の使用が推奨されない理由
妊娠中および授乳中の女性は、ホワイトニング施術を控えることが賢明です。これには複数の臨床的理由が存在します。
第一に、薬剤成分の胎児への影響に関するデータの不足です。歯科医院で使用される過酸化水素や過酸化尿素は、微量ではあっても体内に吸収される可能性があり、胎盤を通じて胎児に届くことが考えられます [13]。現時点では、これらの成分の妊娠中の使用に関する十分な臨床データや長期追跡研究が不足しており、安全性が医学的に確立されているとは言えません。医療における予防原則に基づき、どのメーカーも「妊娠中・授乳中は使用しないことが望ましい」と注意書きをしていることから、リスクを避けるために使用を控えるべきとされています [13]。
第二に、妊娠による口腔内環境の不安定化です。妊娠中はホルモンの急激な変化により、唾液の分泌が減少したり、口腔内が酸性に傾きやすくなったりします。また、免疫力も低下し、つわりによる歯磨きの困難さや間食の増加と相まって、歯周病や虫歯のリスクが高まります [13]。このようなデリケートな状態でホワイトニング剤を使用すると、知覚過敏や歯茎の炎症などのトラブルを引き起こす可能性が高まります [13]。
第三に、ホワイトニングは緊急性の低い美容的処置であるため、専門家の間でも、身体と赤ちゃんの健康を最優先し、「出産後に延期するのが安全」という見解が一般的です [13]。
C. 未成年者(特に16歳未満)への制限
ホワイトニングの一般的な対象年齢は16歳以上とされています [12]。これは、小児や高校生の歯(乳歯および永久歯)がまだ成長途中にあるためです。エナメル質が完全に成熟していない状態でホワイトニング剤を使用すると、薬剤が過剰に象牙質や歯髄に浸透し、歯肉が敏感な未成年者にとって、刺激を受けやすくなることが理由です [12]。
D. 既存の人工物(差し歯、詰め物)への影響
ホワイトニング剤は、セラミックやレジンなどの人工物(差し歯、詰め物、被せ物)に対しては一切作用せず、その色調を変化させることはありません [12]。
この事実は、治療計画において重要な意味を持ちます。もし前歯に人工物がある場合、天然歯だけが白くなると、人工物との色の違いが顕著になり、審美性が損なわれます [12]。このため、審美性を確保するためには、ホワイトニング治療で目標の白さを達成した後に、人工物をその新しい白さに合わせて作り直す(再治療する)必要が生じます。これにより、トータルの治療費と治療期間が増加するため、既存の人工物を持つ患者は、治療開始前に全体的な審美目標と予算について歯科医師と詳細に協議することが不可欠です。
E. 妊娠中など禁忌期間中に可能な代替ケア
妊娠中や授乳中など、ホワイトニングができない期間でも、歯の自然な白さを保つために安全に行えるケアとして、PMTC(プロフェッショナルクリーニング)が推奨されます [13]。PMTCは、歯科医院で専用器具と研磨剤を使用し、歯石やプラーク、日常で付着したステイン(着色汚れ)を除去する処置です。これは歯の表面を磨き上げ、本来の自然な白さとツヤを取り戻す効果があり、虫歯や歯周病の予防にもつながります。妊娠中の安定期(中期)に取り入れることが推奨されており、痛みや刺激に配慮した施術が可能です [13]。
VII. 結論と推奨事項
本レポートは、歯のホワイトニングに関する最も頻繁に寄せられる質問に対し、医療的な作用機序、効果の限界、リスク管理、および長期的なメンテナンス戦略に基づいた専門的な知見を提供しました。
総括的提言:
ホワイトニングは、国家資格者による管理下で行われる医療行為であり、その効果(漂白)は、表面清掃に留まるセルフホワイトニングとは根本的に異なります [1]。最大の効果と持続性を求める場合は、即効性と持続性を兼ね備えたデュアルホワイトニングが、長期的な視点で見ると最も費用対効果の高い選択肢となり得ます [2, 3]。
安全性を確保し、知覚過敏のリスクを最小限に抑えるためには、施術前に虫歯や歯周病、歯のクラックといった既存の口腔内疾患を必ず治療し、歯の構造的な欠陥がない状態にすることが最も重要です [4]。知覚過敏が発生した場合は、硝酸カリウムを含む専門の抑制剤や鎮痛剤を適切に使用し、冷たいものや熱いものといった刺激を避けることで、一過性の症状を効果的に管理することが可能です [4]。
また、効果の維持期間は、施術後の24〜48時間の食事管理に強く依存します。ペリクル剥離後の再着色リスクを避けるため、着色性の高い飲食物、酸性の強い飲食物、そしてイソフラボンを含む大豆製品を徹底して避けることが、白さを長期間保つための鍵となります [5, 6]。長期メンテナンスにおいては、ポリリン酸ナトリウムによる再着色抑制と、ハイドロキシアパタイトによる歯質修復を組み合わせた、二重の化学的アプローチが推奨されます [9]。
特定の禁忌対象者(妊娠中、授乳中、未成年など)については、安全性が確立されていない非必須の審美処置を控え、PMTCなどの安全な代替ケアを選択することが、医療上の原則に基づいた賢明な判断とされます [12, 13]。