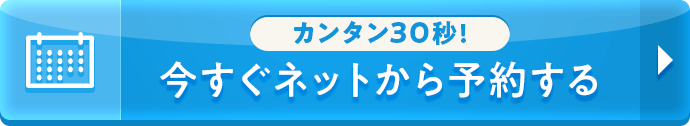静岡県民の歯の意識の調査をしてみました
投稿日:2025年08月12日
最終更新日:2025年08月11日
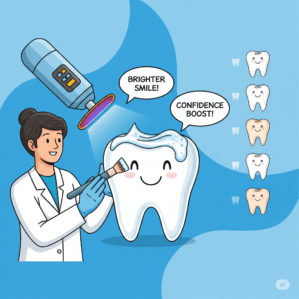
静岡県における歯の意識調査
序章:静岡県における口腔保健の重要性と背景
本報告書は、静岡県における県民の歯と口腔の健康意識の実態、および県が実施している関連調査の結果を包括的に分析するものである。口腔の健康は、単に咀嚼や発音といった機能的な側面に留まらず、全身の健康状態と密接に連携していることが、近年の研究により強く認識されている。この認識は、静岡県が口腔保健推進を公衆衛生上の優先課題として位置づけ、多角的な取り組みを進める上での基盤となっている。
口腔健康と全身の健康の関連性
口腔の健康状態が全身の健康に与える影響は広範かつ深刻である。例えば、歯の欠損が多い個人は全身の健康状態が悪化する傾向にあり、メタボリックシンドロームのリスクが増加するというデータが示されている [1]。これは、十分な咀嚼ができないことで栄養摂取に偏りが生じたり、消化器系への負担が増大したりするなど、間接的に全身の代謝状態に影響を及ぼす可能性を示唆している。
さらに、世界保健機関(WHO)の報告によれば、口腔疾患は糖尿病、アルツハイマー型認知症、脳卒中といった主要な慢性疾患と並び、高齢者の健康寿命を損なう10大原因の一つに挙げられている [2]。この事実は、口腔健康の維持が、高齢化が進む社会において、健康寿命の延伸という喫緊の課題に直接的に貢献する、極めて重要な公衆衛生上の課題であることを浮き彫りにしている。したがって、口腔保健への投資は、単なる歯科治療の枠を超え、慢性疾患の予防と高齢者の生活の質の向上に不可欠な要素として位置づけられるべきである。
静岡県における口腔保健推進の枠組みと取り組みの全体像
静岡県は、県民の口腔健康を包括的に推進するため、明確な政策枠組みを構築している。その中心となるのが「第3次静岡県歯科保健計画」であり、この計画は「歯・口腔に関する健康格差の縮小」、「歯科疾患の予防・重症化予防」、「生活の質の向上に向けた口腔機能の獲得・維持・向上」を主要な柱としている [2, 3]。この計画では、口腔保健の推進には「調査及び研究」が不可欠であると明記されており、歯科に関する統計調査や分析結果の公表を通じて、市町への技術的支援を行う方針が示されている [3]。
県内の主要な市町も、県の計画と整合性を図りつつ、それぞれ独自の歯科口腔保健計画を策定し、地域の実情に応じた取り組みを進めている。例えば、静岡市は「静岡市歯と口腔の健康づくり推進計画(はつらつスマイルプラン)」を策定し、「いつでもだれでもどんなときも歯と口の健康づくりに取り組み美味しく楽しく安全に口から食べることができるまちしずおか」という市民中心のスローガンを掲げている [3, 4]。この計画は、科学的根拠に基づいた施策展開を重視する姿勢を示している。同様に、清水町も「一生おいしく食べて楽しく話せるように口の健康づくりをしましょう」という目標を設定し、地域に根ざした歯科保健行動計画を推進している [5]。沼津市も「第2次沼津市歯科口腔保健計画」を策定し、県計画との整合性を図っている [6]。
これらの多層的かつ協調的な政策枠組みの存在は、静岡県が包括的な目標を設定し、それを各市町が地域の状況に合わせて具体的に実施するという、構造化された公衆衛生ガバナンスモデルを確立していることを示唆する。このアプローチは、広範な政策指令と、それに基づく地域に合わせたきめ細やかな実施の両方を可能にし、様々なレベルの自治体が口腔保健に強くコミットしていることを裏付けている。さらに、静岡市や清水町のスローガン、および県計画の柱が示すように、口腔保健の目標は単なる疾患予防に留まらず、「食べる喜び、話す楽しみ」といった生活の質(QOL)の向上へと明確にシフトしている。これは、口腔健康が日々の生活の充実や社会参加、健康的な高齢化に不可欠な要素として認識されていることを意味し、より幅広い介入を可能にする戦略的転換である。
静岡県民の歯と口腔の健康意識の実態
この章では、静岡県民の歯と口腔の健康に関する意識、特に予防行動や知識の現状を、各種調査データに基づいて詳細に分析する。
定期歯科健診の受診状況と年代別傾向
静岡市が令和4年に実施した「健康・食育に関する意識アンケート調査」(1~84歳対象、回答率43.5%)によると、定期歯科健診の受診率は全体的に改善傾向にある [7]。特に、思春期(13~19歳)では2016年の57.4%から2022年には69.0%へと顕著に増加し、目標値を上回る成果を見せている。高齢者層においても、65~74歳で47.5%から55.8%、75歳以上で51.8%から59.2%へと受診率が向上している [7]。
しかしながら、成人期、特に20代では受診率が28.2%から37.1%に改善したものの、他の年代に比べて依然として低い水準に留まっている。30~44歳(40.2%から51.2%)および45~64歳(40.7%から48.5%)も同様に改善は見られるものの、さらなる向上が求められる [7]。沼津市が令和元年に実施した「第46回市民意識調査」(18歳以上対象、回答率46.0%)でも同様の傾向が確認されており、定期的な歯の検診を「受けている」と回答した人は全体の43.0%であったが、年代別では10代が52.9%と最も高く、20代で31.7%に低下し、その後年齢が高くなるにつれて再び高くなる傾向が見られる [6]。これらのデータは、10代や高齢者層で受診率が向上しているにもかかわらず、20代から30代にかけて定期歯科健診の受診率が顕著に低下するという一貫したパターンを示している。これは、この年代がキャリア形成や子育てなどで多忙であり、自身の健康管理が後回しになりがちなライフステージの特性を反映している可能性がある。
全国的なデータとして、厚生労働省の「令和6年歯科疾患実態調査」では、過去1年間の歯科検診受診割合が63.8%であり、女性の方が男性よりも受診率が高いと報告されている [8]。静岡県内のデータは、この全国平均と比較して、成人期の特定の年代層で受診率に課題があることを示唆しており、より詳細な分析と対策の必要性が浮き彫りになる。
検診受診を促進するための具体的な施策として、富士市では令和7年度に特定の年齢層(20, 30, 40, 50, 60, 70歳)の市民を対象とした歯周病検診を実施しており、自己負担金800円で受診可能だが、生活保護受給者は無料となる [9]。焼津市でも成人歯科健診が特定の年齢層と妊婦を対象に500円の自己負担金で提供され、70歳、後期高齢者医療制度加入の65歳、生活保護受給者、市民税非課税世帯は無料となる [10]。これらの取り組みは、費用が受診の障壁となりうることを県や市町が認識し、経済的要因による健康格差を是正しようと意図的に政策を設計していることを示している。このような費用負担軽減策は、予防医療へのアクセス公平性を高める上で重要であり、その効果を最大化するためには、対象者への周知徹底と、無料化の対象とならないが経済的に困難を抱える層への追加支援の検討が必要となる。
| 市町村名/調査年 | 10代 | 20代 | 30代~44代 | 45代~64代 | 65代~74代 | 75代以上 | データソース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡市 (R4) | 69.0% | 37.1% | 51.2% | 48.5% | 55.8% | 59.2% | [7] |
| 沼津市 (R1) | 52.9% | 31.7% | – | – | – | 52.2% | [6] |
| 全国平均 (R6) | – | – | – | – | – | 63.8% (全体) | [8] |
*注:沼津市の調査は年代区分が異なるため、直接比較できない部分がある。全国平均は全体値であり、年代別データは提供されていない。
口腔衛生習慣(歯間清掃用具の使用、フッ化物利用など)
口腔衛生習慣に関する調査では、沼津市の市民意識調査において、デンタルフロスや歯間ブラシなどの「歯間清掃用具」を「毎日使う」または「週1回以上使う」と習慣的に使用する人は全体の43.4%に留まっている [6]。この傾向は、20代~30代で特に使用率が低いことが指摘されており、基本的な歯磨き以外の、より高度な口腔ケア習慣の普及に課題があることを示唆している。一方で、静岡市の調査では、中学生の歯間清掃用具使用率は2016年の41.6%から2022年には51.5%へと改善しており、若年層での意識向上が見られる点は評価できる [7]。
フッ化物利用に関しては、静岡市の調査で、中学生・高校生では69.4%(令和1年)、40歳以上では37.8%(令和1年)の利用率が報告されており、次回の調査が令和7年に予定されている [7]。フッ化物の利用はう蝕予防に科学的に有効であると広く認識されている [3, 11]。しかし、学校でのフッ化物洗口の実施については、令和3年度の養護教諭向けアンケートで、「人手不足、薬剤管理の難しさ、時間不足」といった運用上の課題が挙げられている [7]。さらに、新型コロナウイルス感染症の影響で、歯科専門職による学校での健康教育が控えられていたことも指摘されており、これが口腔衛生習慣の指導機会減少につながった可能性が考えられる [12]。
定期歯科健診の受診率が向上している一方で、歯間清掃用具の習慣的利用率が依然として低いことは、県民が専門家によるケアの重要性を認識し始めているものの、日々の自宅でのより高度な予防習慣が十分に定着していないことを示唆している。公衆衛生キャンペーンは、単に歯科受診を促すだけでなく、デンタルフロスや歯間ブラシといった特定の口腔衛生ツールの日常的な使用を積極的に教育し、実践を促す必要がある。また、フッ化物利用率の向上、特に学齢期の子どもたちにおいては、政策立案者が学校での運用上の障壁に積極的に対処する必要がある。これには、学校への追加的な資源提供、プロトコルの簡素化、または家庭でのフッ化物配合歯磨剤の使用促進など、代替的な普及方法の検討が含まれるべきである。
口腔健康に関する知識と認知度(8020運動、オーラルフレイル、喫煙の影響など)
静岡市の調査では、「喫煙が歯周病に影響することの認知度」が2016年の29.6%から2022年には79.7%へと大幅に向上しており、特定の健康リスクに関する意識啓発が成功していることが示されている [7]。これは、特定の健康リスクに対する集中的な啓発キャンペーンが非常に効果的であることを明確に示している。
一方で、「8020運動の認知度」(40歳以上で51.4%、令和1年)や「オーラルフレイルの認知度」(40歳以上で11.5%、令和1年)、「はつらつスマイル運動の認知度」(40歳以上で37.9%、令和1年)は、まだ改善の余地がある [7]。特に「オーラルフレイル」の認知度は非常に低い水準にあり、静岡県全体のデータでも24.8%(2022年)と目標値50%に達していない [13]。これは、県民が直接的な因果関係(喫煙と歯周病)は理解しやすい一方で、より複雑で包括的な健康概念(オーラルフレイル)については、さらなる啓発が必要であることを示唆している。
「8020達成者」(80歳で20本以上の歯が残っている人の割合)は、全国平均で61.5%(75~85歳で推計)であるのに対し [8]、静岡県では2021年時点で68.4%と全国平均を上回っており、目標値85%に向けて着実に進捗している [13]。これは、長年の8020運動の成果が着実に現れていることを示している。今後の公衆衛生キャンペーンでは、「オーラルフレイル」とその全身健康への影響について、より分かりやすく、かつ継続的な情報発信を優先すべきである。喫煙に関する啓発キャンペーンの成功事例から学び、多角的なアプローチで認知度向上を図る必要がある。
静岡県の歯科口腔健康に関する調査結果の分析
この章では、静岡県における具体的な口腔健康指標の現状と、それらが示す課題をライフステージ別に掘り下げて分析する。
ライフステージ別口腔健康指標の現状と課題
静岡県では、ライフステージごとに異なる口腔健康課題が浮上している。
乳幼児・学齢期
3歳児における4本以上のう蝕のある歯を有する者の割合は2.2%(2021年度)であり、2035年度の目標値0.7%達成にはさらなる努力が求められる [13]。同様に、5歳児で乳歯むし歯を経験した者の割合は22.7%(2022年度)で、目標値10%との間に大きなギャップが存在する [13]。これは、乳幼児期のう蝕予防が依然として重要な課題であることを示している。一方で、12歳児でう蝕のない者の割合は82.2%(2022年度)と比較的高い水準にあるものの、2035年度の目標値90%達成には継続的な取り組みが求められる [13]。中学校3年生で歯肉に炎症所見(G+GO)を有する者の割合は19.0%(2022年度)であり、目標値15%に向けて改善が必要である [13]。これは、思春期における歯肉炎の予防と早期介入の重要性を示唆している。
新型コロナウイルス感染症の影響で、学校が歯科医師等の外部講師を招いた健康教育を控える傾向にあった時期があり、これにより「歯科専門職による歯の健康教育を行っている小学校・中学校・高等学校」の指標が悪化したと指摘されている [12]。これは、パンデミックが直接的に学校での歯科保健教育の機会を奪い、その結果として学齢期の口腔健康指標に潜在的な悪影響を与えた可能性を示唆する。これに対応するため、静岡市では小学生向けの啓発動画作成などの新規事業を開始し、教育機会の確保に努めている [12]。このような状況は、パンデミックのような大規模な社会変動時にも、学校歯科保健教育の継続性を確保するためのレジリエンスのあるプログラム設計が必要であることを示している。
成人期
20歳代における歯肉に炎症所見を有する者の割合は29.2%(2021年度)であり、目標値20%に向けて改善が求められる [13]。沼津市の調査でも、20代・30代で歯磨き時の出血が見られる割合が高い(30代で30.4%、20代で28.6%)ことが報告されており、若年成人期からの歯周病初期症状の管理が重要である [6]。40歳代で歯周炎を有する者の割合は49.8%(2021年度)と非常に高く、目標値25%との乖離が大きい [13]。これは、成人期の歯周病が県全体の口腔健康における最大の課題の一つであることを示している。未処置のう蝕を有する者の割合も、40歳で39.0%、50歳で36.1%、60歳で33.4%、70歳で34.1%(いずれも2021年度)と、全ての成人年代で目標値10%を大きく上回っている [13]。これは、成人期におけるう蝕の放置が依然として広範な問題であることを示唆している。
これらのデータは、口腔疾患の主要な負担が小児期のう蝕から成人期の歯周病へと移行していることを示唆している。幼少期の予防努力が一定の成果を上げている一方で、成人期における継続的な予防と治療の重要性が増している。公衆衛生戦略は、成人期の歯周病予防と管理に焦点を強化する必要がある。
高齢期
80歳で自分の歯が20本以上ある者の割合(8020達成率)は68.4%(2021年度)であり、全国平均(61.5%)を上回っている [8, 13]。これは、長年の8020運動の成果が着実に現れていることを示している。目標値は85%(2035年度)である [13]。静岡市の調査では、65歳以上の高齢者における口腔機能症状がない者の割合が、2019年の52.0%から2022年には80.1%へと大幅に改善し、目標値52.8%を大きく上回る成果を達成している [7]。これは、オーラルフレイル対策や口腔機能維持・向上への取り組みが奏功している可能性を示唆している。沼津市の調査では、年齢が上がるにつれて自分の歯の喪失が増加し(20代で28本以上が82.5%に対し、60代で25.1%)、噛んで食べられる食品が減少する傾向が確認されている [6]。通院が困難な高齢者や寝たきりの方のために、「静岡県在宅歯科医療推進室」が電話やファクスでの相談を受け付け、訪問診療が可能な歯科医院の情報提供を行っている [3]。高齢者の8020達成率や口腔機能改善の進展は顕著な成果であるが、在宅歯科医療推進室や障害者歯科保健センターの存在は、全体的な改善にもかかわらず、通院が困難な特定の脆弱な高齢者や障害者層にとって、口腔ケアへのアクセスが依然として大きな課題であることを示唆している。地域における健康格差を解消するためには、訪問歯科診療のさらなる充実や、介護施設・福祉施設との連携強化など、特定のニーズを持つ層へのアウトリーチとサービス提供を強化する必要がある。
地域間の健康格差と社会経済的要因の影響
静岡県の歯科保健計画では、「歯・口腔に関する健康格差の縮小」が最終目標の一つとして明確に掲げられており、地域格差や経済格差による健康格差の存在を認識している [2, 3]。特に、う蝕の有病率などにおいて県内市町ごとの地域差が存在することが指摘されており、県はこれらの状況を把握し、関係団体と連携して市町の取り組みを効果的に支援する方針である [2]。
「社会経済的要因が多数う蝕に影響する」という認識があり、これが口腔健康格差の大きな課題となっている [2]。静岡県は、「静岡県国保データベース(SKDB)等を用いたデータ分析報告書」を活用し、地域の実情に応じた歯科医療提供体制の構築を進めている [3]。このデータベースは、地域ごとの健康状態や医療利用状況を詳細に分析し、格差是正のためのエビデンスを提供する重要なツールである。静岡県の歯科保健計画が「健康格差の縮小」を主要目標とし、さらに「社会経済的要因」がう蝕に影響を与えることを明確に認識している点は重要である。SKDBを用いたデータ分析を通じて、市町ごとのう蝕有病率などの地域差を把握し、それに基づいて市町を支援する方針は、健康格差に対して受動的ではなく、能動的かつデータに基づいたアプローチを取っていることを示している。このアプローチは、複雑な健康の社会的決定要因を認識し、より公平な公衆衛生を実現するための成熟した戦略である。
| 口腔健康指標 | ライフステージ/対象年齢 | 現状値 (調査年) | 目標値 (目標年) | データソース |
|---|---|---|---|---|
| 3歳児で4本以上のう蝕のある歯を有する者の割合 | 3歳児 | 2.2% (2021) | 0.7% (2035) | [13] |
| 5歳児で乳歯むし歯を経験した者の割合 | 5歳児 | 22.7% (2022) | 10% | [13] |
| 12歳児でう蝕のない者の割合 | 12歳児 | 82.2% (2022) | 90% (2035) | [13] |
| 中学校3年生で歯肉に炎症所見を有する者の割合 | 中学校3年生 | 19.0% (2022) | 15% | [13] |
| 20歳代における歯肉に炎症所見を有する者の割合 | 20歳代 | 29.2% (2021) | 20% | [13] |
| 40歳で歯周炎を有する者の割合 | 40歳 | 49.8% (2021) | 25% | [13] |
| 40歳で未処置のう蝕を有する者の割合 | 40歳 | 39.0% (2021) | 10% | [13] |
| 50歳で未処置のう蝕を持つ者の割合 | 50歳 | 36.1% (2021) | 10% | [13] |
| 60歳で未処置のう蝕を持つ者の割合 | 60歳 | 33.4% (2021) | 10% | [13] |
| 70歳で未処置のう蝕を有する者の割合 | 70歳 | 34.1% (2021) | 10% | [13] |
| 80歳で自分の歯が20本以上ある者の割合 | 80歳 | 68.4% (2021) | 85% | [13] |
| 口腔機能症状がない者の割合 | 65歳以上 | 80.1% (2022) | 52.8% (目標達成) | [7] |
| オーラルフレイルの認知度 | 40歳以上 | 24.8% (2022) | 50% | [13] |
| かかりつけ歯科医を持つ者(定期管理を受けている者)の割合 | 全体 | 58.5% (2022) | 95% | [13] |
静岡県および各市町の歯科保健推進施策と事業評価
この章では、静岡県全体および各市町で実施されている具体的な歯科保健推進施策と、それらの事業がどのように評価され、改善されているかについて詳述する。
静岡県歯科保健計画の重点施策と進捗
静岡県の歯科保健計画は、歯科口腔保健を担う「人材確保・育成」、「調査及び研究」、「正しい知識の普及」、「歯科口腔保健を担う者の連携及び協力」を重点施策として掲げている [2, 3]。これらは、持続可能な口腔保健システムの基盤を強化するための重要な要素である。県健康福祉センターは、地域歯科会議の開催を通じて必要な歯科保健施策に関する情報提供や技術的支援を行い、市町の取り組みを側面からサポートしている [2, 3]。これは、持続的な口腔健康改善には、熟練した専門家、エビデンスに基づいた政策立案、そして組織間の協力といった強固な基盤が不可欠であるという深い理解を示している。
また、高齢者や寝たきりの方など、通院が困難な県民のために、「静岡県在宅歯科医療推進室」が設置されており、歯科に関する相談窓口として機能し、必要に応じて訪問診療が可能な歯科医院の情報を提供している [3]。これは、アクセス困難な層への支援を強化する具体的な取り組みである。
静岡市、沼津市、清水町等の具体的な歯科保健事業の紹介と効果
静岡市では、「静岡市口腔保健支援センター」を中心に、乳幼児から高齢者まで全てのライフステージに対応した多様な歯科保健事業を実施している [11]。
- 乳幼児・学齢期向け: 9か月児とその保護者を対象とした「9か月児歯の教室」、こども園・保育園・幼稚園の園児を対象とした「歯みがき教室」など、早期からの予防教育に力を入れている [11]。
- 成人期向け: 葵区・駿河区在住の40歳以上の男女を対象とした歯周病検診(自己負担600円)を実施している [14]。また、新型コロナウイルス感染症の影響で学校での健康教育が減少したという課題に対し [12]、小学生向けの啓発動画を作成し、教育機会の確保に努めている [12]。この迅速な対応は、予期せぬ外部要因に対しても柔軟かつ積極的に対応し、公衆衛生サービスを維持しようとする能力を示している。
- 高齢期向け: 10人以上の高齢者グループを対象とした出張型の「歯つらつ健口講座」を実施し、口腔機能の維持・向上を支援している [11]。
- 特別な配慮が必要な対象者向け: 歯科医院への通院が困難な方を対象とした「訪問歯科診療支援事業」を実施している [11]。また、静岡市障害者歯科保健センターは、心身に障がいのある方で一般歯科診療所での治療が困難な方への歯科支援を提供している [15]。浜松市にも同様に、車椅子やストレッチャー対応、薬物的行動調整が可能な「口腔保健医療センター歯科室」があり、障害者歯科学会の有資格者が対応している [16]。浜松市と静岡市に設置されている障害者歯科保健センターや、静岡県の在宅歯科医療推進室は、一般の歯科診療所では対応が困難な人々に対して、専門的な歯科医療や相談サービスを提供している。これは、健康格差の解消という目標を達成するために、特に脆弱な住民層へのアクセスと専門的ケアの確保に重点を置いていることを明確に示している。
静岡市が乳幼児から高齢者、さらには通院困難者や障害者といった特定のニーズを持つ層まで、非常に多様なプログラムを展開していることは注目に値する。これは、「ライフコースアプローチ」の概念を具現化したものであり [7]、個人の生涯にわたる健康課題にきめ細かく対応しようとする意図が明確である。この包括的なアプローチは、画一的な施策よりもはるかに効果的である可能性が高く、各ライフステージや特定の集団が抱える固有の口腔健康課題に対応することで、より高い介入効果が期待できる。
| 事業名 | 実施主体 | 対象者 | 主な活動/サービス内容 | データソース |
|---|---|---|---|---|
| 9か月児歯の教室 | 静岡市 | 9か月児とその保護者 | 歯の健康教育 | [11] |
| 歯みがき教室 | 静岡市 | こども園・保育園・幼稚園の園児 | 歯みがき指導 | [11] |
| 歯つらつ健口講座(出張型) | 静岡市 | 10人以上の高齢者グループ | 口腔機能の維持・向上に関する講座 | [11] |
| 訪問歯科診療支援事業 | 静岡市 | 歯科医院へ通院困難な方 | 訪問歯科診療の支援 | [11] |
| 歯周病検診 | 静岡市(葵区・駿河区) | 40歳以上の男女 | 歯科医師による検診、自己負担600円 | [14] |
| 成人歯科健診 | 焼津市 | 20,25,30…70歳になる市民、妊婦 | 問診、歯科診察、口腔内診査、自己負担500円(一部無料) | [9, 10] |
| 静岡県在宅歯科医療推進室 | 静岡県 | 高齢や寝たきり等で通院できない方 | 歯科に関する相談、訪問診療可能な歯科医院情報提供 | [3] |
| 静岡市障害者歯科保健センター | 静岡市 | 心身に障がいのある方で一般歯科診療困難な方 | 歯科診療、歯や口に関する相談 | [15] |
| 口腔保健医療センター歯科室 | 浜松市 | 障害者、障害児、全身疾患、要介護、摂食困難者 | 専門歯科診療(車椅子対応、鎮静法、全身麻酔等) | [16] |
| 小学生向け啓発動画の作成 | 静岡市 | 小学生 | 歯の健康教育動画の提供 | [12] |
地域連携と多職種協働の取り組み
静岡県の歯科口腔保健推進計画では、「歯科医療職間・医科歯科連携を始めとする関係職種間・関係機関間の連携」が重要な要素として明記されている [7]。これは、口腔健康が全身健康と密接に関連しているという認識に基づき、多角的なアプローチが必要であるという理解があるためである。県は、歯科医師会や歯科衛生士会などの歯科専門団体、および市町と連携し、オーラルフレイルの周知啓発など、特定の課題に対する共同の取り組みを推進している [2, 3]。
教育機関もこの連携を重視している。静岡県立大学短期大学部の歯科衛生学科では、「保健医療と福祉の連携による教育」を特色とし、地域歯科保健の推進者として活躍できるよう、他職種と連携・協力できる知識と態度を養うことを目標としている [17, 18]。専門学校中央医療健康大学校の歯科衛生学科のカリキュラムにも「全身疾患と口腔ケア」が含まれており、医科歯科連携を意識した教育が行われている [18]。これらの教育への組み込みは、口腔保健が全身の健康の一部として認識され、将来的に医療・福祉システム全体でよりシームレスな連携が実現されることを示唆する。これにより、患者中心の包括的なケアが促進され、より良い公衆衛生アウトカムに繋がる可能性が高い。
結論と提言:持続可能な口腔保健推進に向けて
これまでの取り組みの成果と残された課題の総括
静岡県は、多層的かつ協調的な歯科保健計画に基づき、乳幼児期から高齢期まで幅広いライフステージに対応した多様な事業を展開している。特に、思春期および高齢者層における定期歯科健診受診率の向上、8020達成率の全国平均超え、高齢者の口腔機能改善、そして喫煙と歯周病の関連性に関する県民の認知度向上は顕著な成果である [7, 8, 13]。これらの成果は、県および市町が口腔保健を公衆衛生上の重要課題と認識し、継続的な努力を重ねてきた結果であると評価できる。また、新型コロナウイルス感染症のような予期せぬ事態に対しても、デジタル教材の導入など柔軟な対応を見せている [12]。
しかしながら、いくつかの重要な課題も依然として残されている。若年成人層(20代~30代)における定期歯科健診受診率の低さは継続的な課題であり、この年代の多忙なライフスタイルに合わせた介入策が求められる [7, 6]。また、歯間清掃用具の習慣的な使用率が依然として低いことや、オーラルフレイルといった新しい口腔健康概念の認知度が低いことも、今後の啓発活動の重点領域となる [6, 13]。さらに、乳幼児期や成人期のう蝕有病率、および成人期の歯周炎有病率は依然として目標値を大きく上回っており、特に成人期の歯周病が口腔疾患の主要な負担となっている現状がある [13]。学校におけるフッ化物洗口プログラムの運用上の課題(人手不足、薬剤管理、時間不足)も、科学的根拠に基づく予防策の普及を阻害する要因として認識されている [7]。最後に、全体的な指標の改善が見られる一方で、通院が困難な高齢者や障害者といった特定の脆弱な住民層へのアクセス確保は、引き続き重要な課題である [3, 15, 16]。
今後の口腔保健推進に向けた提言
上記の分析に基づき、静岡県における持続可能な口腔保健推進に向けて、以下の提言を行う。
- 若年成人層へのターゲットを絞った受診促進策の強化: 20代~30代の定期歯科健診受診率向上のため、職域連携による健診機会の拡充、オンラインを活用した情報提供、またはライフイベント(結婚、出産など)に合わせた歯科保健情報の提供など、この年代のニーズに特化したアプローチを開発・実施すべきである。
- 高度な口腔衛生習慣の普及と実践支援: 単なる歯磨きだけでなく、デンタルフロスや歯間ブラシといった歯間清掃用具の日常的な使用を促すための、より実践的かつ継続的な教育プログラムを推進する必要がある。行動変容を促すための具体的なインセンティブや、歯科専門職による個別指導の機会を増やすことも有効である。
- 新たな口腔健康概念の認知度向上と啓発戦略の再考: 「オーラルフレイル」など、全身健康に直結する新しい口腔健康概念について、県民が理解しやすいように、多角的なメディアを活用した継続的な情報発信を強化すべきである。喫煙と歯周病の関連性に関する啓発キャンペーンの成功事例を参考に、効果的なメッセージングと普及チャネルを検討することが望ましい。
- ライフステージ別課題への集中的な介入:
- 乳幼児・学齢期: う蝕有病率の目標達成に向けて、学校におけるフッ化物洗口プログラムの運用上の課題(人手不足、薬剤管理、時間不足)に対し、追加的な資源提供やプロトコルの簡素化、あるいは家庭でのフッ化物配合歯磨剤の使用促進など、具体的な解決策を講じるべきである。
- 成人期: 歯周病の早期発見と治療、および未処置う蝕の解消に焦点を当てた健診・治療促進キャンペーンを強化する必要がある。
- 健康格差解消に向けたアクセス改善の継続: 全体的な口腔健康指標の改善に満足することなく、通院が困難な高齢者や障害者、要介護者など、特定のニーズを持つ脆弱な住民層への訪問歯科診療のさらなる充実、介護施設・福祉施設との連携強化、および専門的な歯科医療提供体制のアウトリーチを強化すべきである。
- データ駆動型政策立案の深化: 静岡県国保データベース(SKDB)のような既存のデータ基盤をさらに活用し、地域ごとの詳細な健康格差を継続的に分析することで、限られた資源を最も効果的に配分し、真に支援が必要な地域や集団に焦点を当てた施策展開を推進すべきである。
これらの提言を実行することで、静岡県は県民の口腔健康水準を一層向上させ、結果として健康寿命の延伸と生活の質の向上に貢献できるものと考える。
歯科医師 岡本恵衣

経歴
2012年:松本歯科大学歯学部を卒業
2013年:医療法人スワン会スワン歯科で研修
2014年:医療法人恵翔会なかやま歯科に勤務
2020年:WhiteningBAR(株式会社ピベルダ)に勤務