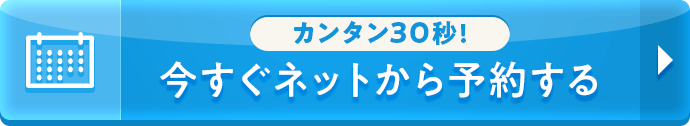歯を大切に!シリーズ③「口臭」について
投稿日:2023年10月2日
最終更新日:2023年10月3日

セルフホワイトニングに興味がある皆さんと一緒に歯について学ぶシリーズ、第3回目のテーマは「口臭」です。
まわりの人に不快感を与えているかも…。
治す方法がわからない…。
口臭が気になり始めたら、楽しくおしゃべりができなくなってしまいますね。
恥ずかしくて誰にも相談できないまま、自身の口臭に悩み続けていませんか?
口臭には「生理的口臭」「病的口臭」「食餌性口臭」があり、どれに当てはまるのかわかれば改善できるはず。
今回は口臭の原因と対策について解説します。
口臭にお悩みの方は参考にしてください。
目次
口臭の種類
◉生理的口臭
主な原因は唾液不足です。
唾液には、口臭を引き起こす口内の細菌を包み込んで胃に流し、細菌の繁殖を防ぐ役割があります。
唾液の分泌量が減ると、揮発性硫黄化合物が発生、細菌が繁殖、臭いを引き起こします。
朝起きた直後や睡眠中や緊張する場面などは唾液が少ない状態になり、口臭が発生しやすくなります。
口臭を生むバクテリアを抑制するには、キシリトール入りのガムを噛み、唾液の分泌を促すことも効果的です。
また、年齢を重ねると唾液の分泌量が減り口臭が出やすくなるため、注意が必要でしょう。
◉病的口臭
病的口臭の代表的なものが歯周病で、プラークや歯垢と呼ばれる細菌のかたまりが繁殖することで進行してしまいます。
歯周病が重度になると、歯と歯茎の隙間が広がり歯周ポケットができ、そこから出る膿が口臭の元になります。
歯周病以外の原因は、虫歯(う蝕)、歯垢、歯石、舌苔(舌の表面に付くコケ状の細菌の固まり)、唾液の減少、義歯の清掃不良など。
その他、鼻・喉・消化器系・呼吸器系の病、糖尿病、肝臓疾患、口腔カンジダ症などが原因で口臭が起こる場合もあります。
虫歯の場合は、穴が開いた部分に食べ物が詰まり、細菌が広がり、口臭を放ちます。
◉ 食餌性口臭
ニンニクやネギやニラのようにニオイの強い食品を食べた後、歯に挟まった食べカスなどのタンパク質を細菌が分解発酵することで発生するガスが、臭いの原因になります。
エナジードリンクなどの飲み物も、唾液の効果を阻害するため、口臭のリスクがより高まるそうです。
また、お酒やタバコなどは、臭いの元になる成分が胃で消化された後、血液を介して全身を巡り、肺を経由して吐き出されるのだとか。
しかし、食べ物や飲み物や嗜好品による口臭は一時的なものであり、時間が経てば気にならなくなります。
口臭を抑える方法
口臭を抑える方法として
⑴歯を丁寧に磨く
⑵舌苔を除去する
⑶歯医者に相談する
の三つが挙げられます。
⑴歯磨きは、朝・昼・晩の毎食後3回だけではなく、起床時にもできれば理想です。
唾液の分泌量が減少する就寝中は、最も口内に細菌が繁殖しやすくなっているため、朝一番には丁寧に磨きましょう。
歯の表面はもちろん、裏側や歯と歯の間にも歯ブラシがきちんと当たるようにして、食べカスや歯垢が残らないようにします。
歯ブラシは横に大きくスライドさせるよりも、軽い力で細かく振動させながら磨いた方が汚れも落ちやすいようです。
しかし、歯ブラシで取り切れる歯垢は60%程度。
デンタルフロスや歯間ブラシを使い、狭い隙間に入り込んだ汚れもしっかりと取り除けば、80%以上の歯垢を除去することができます。
⑵舌の表面に付着している白い苔のような汚れ、舌苔(ぜったい)も、口臭の原因です。
舌苔の除去には、専用の舌クリーナーや柔らかい歯ブラシを使い、舌の奥から前方に向かってかき出すようにします。
力を入れすぎると舌を傷つけてしまうため、軽い力で1カ所につき3回程度が目安です。
⑶歯医者に相談することも有効でしょう。
大学病院には口臭外来という専門の診療科が設置されており、ガスクロマトグラフィーという装置で精密検査をするそうです。
口臭対策だけではなく、歯や口中に関する知識やノウハウが豊富な専門家ですから、歯周病や虫歯などのトラブルも同時に解決できます。
最後に
口腔内を清潔に保つこと、原因を突き止めることが、口臭予防の基本であると学びました。
原因のひとつである歯周病については、次回、より掘り下げて勉強したいと思います。
美しい口元は健康から!
口腔環境を整えて、歯の白さをより楽しんでいただきたいと思います。
歯科医師 岡本恵衣

経歴
2012年 松本歯科大学歯学部卒業
2013年 医療法人スワン会スワン歯科にて臨床研修
2014年 医療法人恵翔会なかやま歯科
2020年 WhiteningBAR(株式会社ピベルダ)
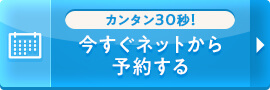





新着情報
2025年9月17日おすすめ記事
コラム一覧
2025年9月15日
町田のホワイトニング完全ガイド:本格クリニックからセルフサロンまで徹底解剖
2025年9月7日
ホワイトニングバー新潟のあるホテルオークラ新潟とは?
2025年9月5日
ホワイトニングを始めるきっかけと継続率についての調査
2025年9月3日
富裕層の歯に対する意識調査
2025年8月31日
初対面で相手のどこを見るか調査
2025年8月27日
歯が白いと異性に好印象!調査で判明した影響とは
2025年8月25日
ホワイトニングのリスクについて
2025年8月25日
サッカー選手とホワイトニングの関係
2025年8月22日
歯に対する意識が高い人の特徴
2025年8月21日
ホワイトニングバーが長年トップランナーであり続けられる理由
2025年8月20日
ホワイトニングの費用はいくらまで?相場と選び方を解説
2025年8月19日
町田市の歯科医療と口腔衛生に関する専門家レポート
2025年8月18日
世界で最も歯のホワイトニングに対する需要が高い国は?
2025年8月13日
都内で探す、身近なセルフホワイトニングガイド